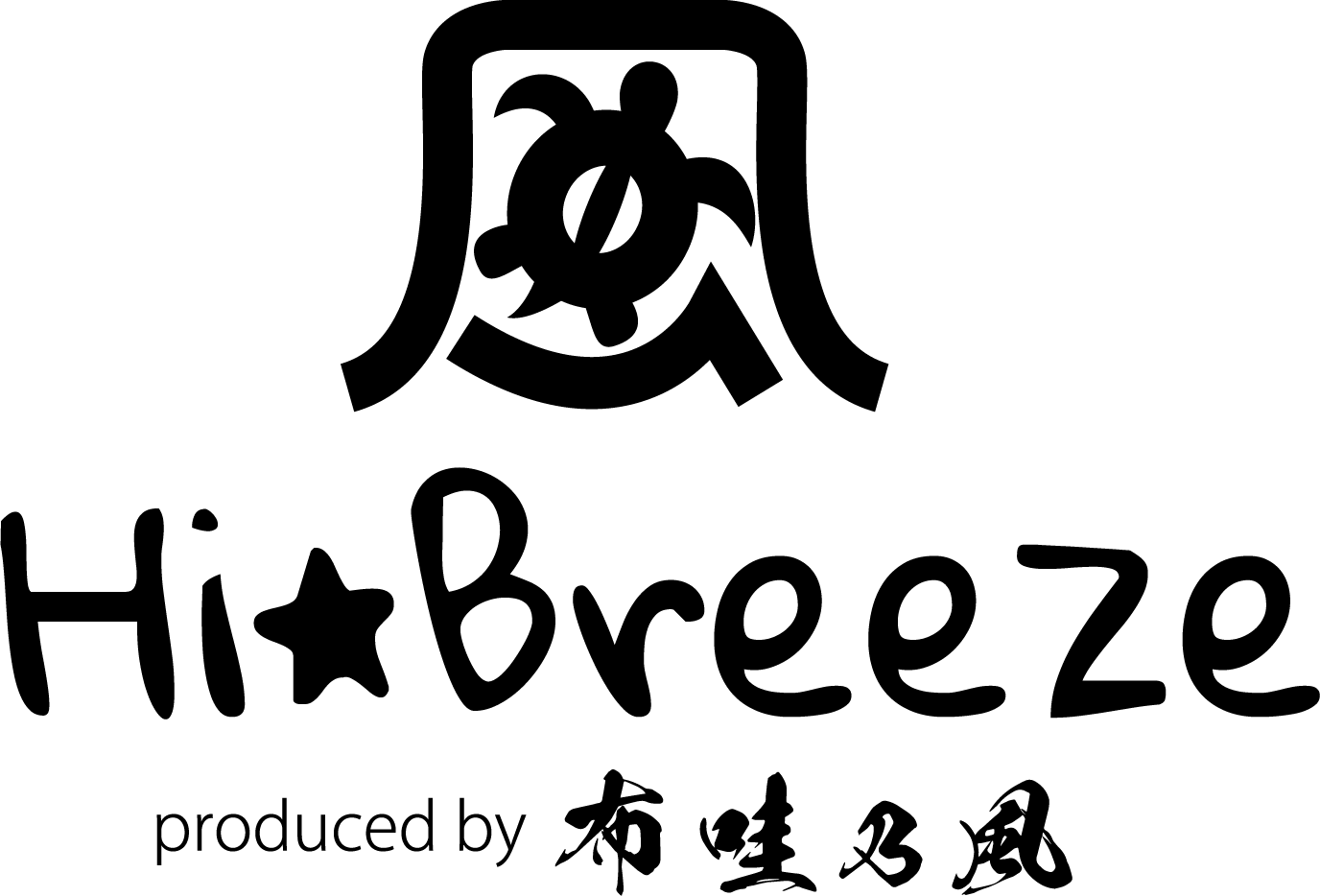2023/04/18 14:41
1991年7月1日。 よく晴れた清々しい朝にホテルを出た新婚ほやほやのぼくたちは、滞在地のワイコロアから北まわりのルートでヒロの町を目指した。 片道およそ3時間の道のりを、寄り道することなく、フロントガラス越しに流れ去る景色を楽しみながらひたすらクルマを走らせた。 ぼくたちにとって、はじめてのBIG ISLANDだった。 カーナビなど無い時代、慣れない経路を地図を確かめながらたどるドライブは道のりを少しばかり長く感じさせた。 19号線を南下し、やがてヒロ湾が視界の左手にひろがると、運転疲れはたちまち消え失せた。 胸が踊った。ついに来たぞ。 この島に来た目的は、なにより、ヒロを訪れることにあったのだから。 町に入ったのは昼前だった。 ヒロは “雨の都” というニックネームがつくほど雨の日が多い。その日は幸運にも快晴に恵まれた。 路上のパーキングスペースにクルマを停め、爽やかな陽光のもと散策に出た。 そこはかとなくノスタルジックな風情のメインストリートは、それまで写真を眺めては頭に描いてきた景観と、かなりの度合いでマッチしていて少しうっとりした。 古き佳きハワイの面影を残す町の佇まいに、この地に渡った日系移民が築いてきた目に見えない歴史の年輪が心に染みいってくるような感覚に包まれ、背筋が伸びた。 すれ違う人は少なく、目に触れるもの、肌に触れる空気、すべてワイキキとは異空間に思えた。ゆっくりと行き過ぎるクルマもクラシカルで、タイムスリップしたような錯覚にとらわれた。 ここを訪れる日本人の多くがきっと、ぼくと同じように在りし日のハワイに思いを馳せるのだろう。 この町に来たら必ず “あの店” に立ち寄ろうと決めていた。 マモストリートとケアウエストリートが交差するコーナーにその店はある。 すでにおわかりの御仁もいらっしゃるだろう。そう、あの店だ。 「ELSIE'S(エルシーズ)」の看板はすぐに見つかった。 そこに自分がいることが、少し不思議だった。 ドアが開いたままの店の前で一度深く息を吐いて敷居をまたいだ。とても感慨深い一歩だった。 そんなぼくらを柔和な笑みをたたえた老夫婦穏が迎えてくれた。 トレードマークの蝶ネクタイ姿に気品が漂うジェームズさんと、やさしく包み込むような温かい眼差しの奥さま、日系2世の篠原夫妻だ。 この店がオープンしたのは1940年だったか。であれば、日本海軍による真珠湾攻撃があったはその翌年。ハワイの日系人社会において筆舌に尽くしがたい劇甚たる事変であったことは想像するに足りない。圧倒的な人生の重みを感じるからこそなおさら、お二人がまとう長閑やかな空気と柔らかな物腰にすっかり魅せられてしまった。 エルシーズと篠原夫妻の存在を知ったのは、片岡義男さんの短編小説『ヒロ発11時58分』だった。小説に描写されたその店が「ELSIE'S」であると、きちんと教えてくれたのは雑誌『POPYE』の1982年に刊行されたイシューだったと思う。それは「ヒロの街角のコーヒーショップ、エルシーズに一日いると、オールドハワイが手に取るように見えてくる」という長いタイトルで始まる記事だった。こんなタイトルを見せつけられたらもう、誰だってそこに行ってみたくなるに違いない。まんまと、その一人にぼくはなった。 片岡さんの小説の主人公は、店に入ってまずコーヒーとドーナツを注文した。ぼくは何を注文したんだっけ。いやはや覚えていない。 店で過ごした時間のほとんどがおぼろかな記憶になってしまったが、つぎのシーンだけは思い出すたびに幸せな気分になる。 その日、ほかに客はひとりもいなかった。いったん店の奥に姿を消した篠原さんは何冊かの古いフォトアルバムを手にして戻ってくると、ぼくたちのテーブルにそれを置いた。そしてページを一枚一枚めくり、色あせた写真を指さしながら、ゆっくりとした口調で遠い昔の思い出を語ってくれた。 残念なことに、情けないことに、話の内容は記憶に残っていない。 けど、あのときの、ゆったりと流れる時間と、篠原夫妻との和やかな会話の心地よさは、感覚としてぼくの脳内のどこかに大切に保管されていて、いつでも呼び起こすことができる。 それから数年後だっただろうか、奥さまがお亡くなりになり、その後、ジェームスさんも泉下の人となられた。 一度しか訪ねられなかったぼくが利いたふうな口をきくのはお門違いだと重々承知しているけど、篠原夫妻がご存命のときにエルシーズでゆったりと楽しいひとときを過ごせたことは、ぼくにとって、べらぼうに貴重で自慢の想い出なんだ。いつまでも大切な。